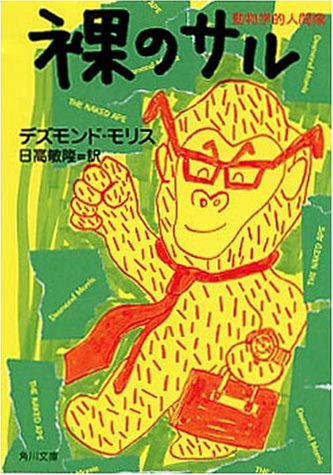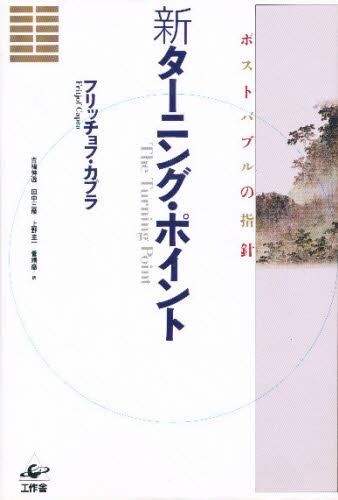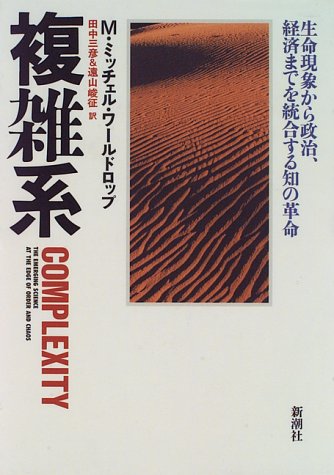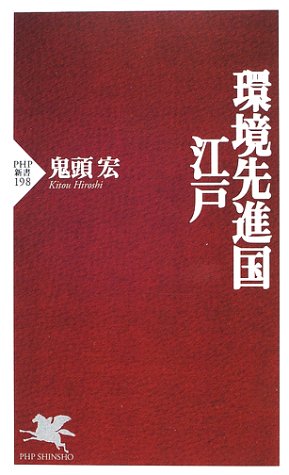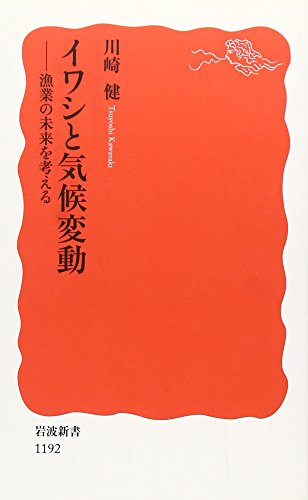菊地 淳(きくち・じゅん)博士
理化学研究所 環境資源科学研究センター
環境代謝分析研究チーム チームリーダー
博士(工学)。1998年、JST・ERATO 研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター、植物科学研究センター・ユニットリーダーおよびチームリーダーを経て2013年4月より環境資源科学研究センター・チームリーダー、横浜市立大学大学院生命医科学研究科・大学院客員教授ならびに名古屋大学大学院生命農学研究科・客員教授。
子ども時代に見た河川水質と生態系の劇的な変動が研究の原点
昔も今も読書好きだが、子どものころは科学の本より歴史ものの小説やマンガを読むことが多かったという菊地チームリーダー(TL)。山が近い東京都の西多摩地区で育った。「毎日、多摩川や秋川の河原で遊んでいました。小学1年生のころは家庭や工場、農地からの排水で富栄養化し濁っていた川が、下水道の整備などが進み中学生のころにはアユの泳ぐ澄んだ川になりました。今から思えば、川の変動を目の当たりにした強烈な体験が、生態系や環境に興味を持つきっかけとなり、現在の研究へとつながったのでしょう」。
人間を含めた「生態系」への関心につながった1冊
大学では生物と化学、そして物質科学を学びたいと考えていた。テニス部に所属していたことや川遊びの延長から、ラケットや釣りざおに使われる最先端材料の開発にも憧れがあったからだ。それらを統合的に学べる学科に進んだ。
「振り返ると、大きな影響を受け最初のターニングポイントになった本が、デズモンド・モリスの『The Naked Ape(邦題: 裸のサル)』です。英語の講義のテキストとして仕方なく読み始めたのですが、すぐに引き込まれました。動物行動学者である著者が、人間は体毛のないサルにすぎないという視点で人間の行動を分析し、人間としての生き方を説いています。興味の対象であった生物と自分自身が一気に近づき、人間も含めた生態系への関心につながりました」。

理系・文系を融合し、複雑系に踏み込むキッカケとなった2冊
大学院に進むと、より専門的な知識や技術を身に付けたいと思う一方、理系だけでいいのだろうか、自然界を研究対象とする理系と人間活動を研究対象とする文系の融合領域こそ面白く、自分がやりたいことなのではないか、という葛藤を感じ始めた。そんなときに読んだのが、フリッチョフ・カプラの『ターニング・ポイント』だ。「著者は物理学者で、西洋的な世界観である還元論から、東洋的な世界観である全体論的な考え方への転換を論じています。理系と文系の融合も全体論的な考え方であり、背中を押してもらったように思えました」。
研究者になるならば新しい分野を切り拓きたい、と思っていた。「全体論とつながるキーワードが、複雑系でした。生態系や環境は多くの要素から成り、互いに影響し合って複雑に振る舞う、まさに複雑系です。科学の王道である還元論的に要素に分けていく方法ではなく、混沌としたものを複雑なまま捉える新しい手法を探ることにしたのです。『ターニング・ ポイント』とミッチェル・ワールドロップの『複雑系』との出会いが私の第二のターニングポイントであり、全体論と複雑系を基調とする研究哲学の構築へとつながりました」。

研究のヒントは、身近な話題が豊富な「新書」から
菊地TLは2004年に理研の研究員となり、その翌年に研究室を立ち上げた。「研究室の主宰者としてやっていくには、新しいアイデアが必要です。研究のヒントは、意外と身近なところにあるものです。そこで、身近な話題を扱っている新書をたくさん読むようになりました。第三のターニングポイントなったのは、このときに読んだ数々の新書でした(例えば、鬼頭宏『環境先進国・江戸』、石弘之・安田喜憲・湯浅赳男『環境と文明の世界史』、川崎川崎健『イワシと気候変動」、井上真由美『カビの常識 人間の非常識』、ほか多数)。農水産業の環境と食、食の代謝と腸内細菌叢、排水処理と環境微生物叢など、身近な話題と先端研究をつなぐことで、社会の関心が高まってくる前にいち早く研究課題を設定できるようになりました」。
そうした過程を経て菊地TLは現在、エコインフォマティクスと名付けた新しい手法で、人間活動を含む環境という複雑系を解析し、その変動を予測しようとしている。ビッグデータの解析には社会科学で用いられる手法も取り入れた。

研究室の本棚に、読了本を並べる理由とは
読んだ本は、研究室の本棚に並べてある。「細部は忘れてしまっても、背表紙を見ると本質的な内容や感じたことを思い出すもので、本は見える場所に並べておくべきだ、という書誌学者・谷沢永一さんの著書を参考にしたのです」。
歴史ものが好きなのは、今も変わらない。「歴史小説には、当時は無名だった人も登場します。なぜ彼らのことが伝えられているかというと、手紙や日記が遺っているからです。私は、自らの足跡を歴史に遺したい。それが論文や本を書くモチベーションになっています。私の研究が今は認められなくても、文書として遺しておけば、将来誰かが見つけて評価してくれるかもしれませんからね」。
(取材・執筆:鈴木志乃/フォトンクリエイト、撮影:STUDIO CAC)